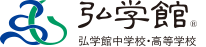弘学館のあゆみ
| 昭和59年11月1日 | 松尾建設株式会社(明治18年創業)の創立100周年記念事業として中高一貫英才教育校の設立を決定。 学園創立の地、佐賀市金立は「葉隠発祥の地」であり、「弘学館」の名も佐賀鍋島藩校「弘道館」にちなんでいる。このことは“現代の藩校”たらんという願いが込められている。 |
|---|---|
| 昭和61年4月28日 | 第1校地造成工事に着手。この日を創立記念日とする。 |
| 昭和62年4月7日 | 開校式に引き続き第1回入学式を挙行。 |
| 昭和63年5月21日 | 松尾建設株式会社寄付による「松尾記念館」完成。 |
| 平成2年3月10日 | 第1期卒業生61名のうち、東京大学へ10名が受験し8名合格。 |
| 平成11年3月10日 | 東京大学に33名が合格し、全国高校別ランキング19位を記録。 |
| 平成14年4月5日 | 高校女子第1期生入学。 |
| 平成19年2月21日 | 校舎棟第3期建設(普通教室棟西側増築)工事完成。 |
| 平成19年4月5日 | 中学女子第1期生入学。 |
学園設立母体
松尾建設株式会社
本学園は、松尾建設株式会社(1885年松尾安兵衛創業)の創立百周年を記念して、地域社会への報恩事業として、この地から世界へ勇躍する若者の出でんことを希い、松尾建設並びに関連四社(松尾舗道 松尾工業 マツオ・ビルエンジニアリング 松尾商事)の幾多の尽力により設立されたものである。
1987年4月 学校法人松尾学園 創設理事長 松尾幹夫
(校庭の一角にそびえるケヤキの樹下に埋め込まれた設立記念碑より)
常に生徒と共にありたい
初代校長 澁谷 敏明
(1932〜2006年)
弘学館設立に尽力し、中高一貫教育の英才教育に、全国でも例を見ない画期的な学寮制を導入する。初代校長となり、短期間で全国有数の進学校に育て上げた。常に生徒と共にありたいと願い「教育の原点は、こども達のために、自分自身をどれだけ犠牲に出来るかということ」をモットーにする。なにごとにも果敢に挑戦する気概を、その優しいまなざしを通して教え続けた澁谷氏の信念は、本校の土壌にしっかりと根付き、幾多の卒業生や生徒たちのなかで立派に実を結んでいる。